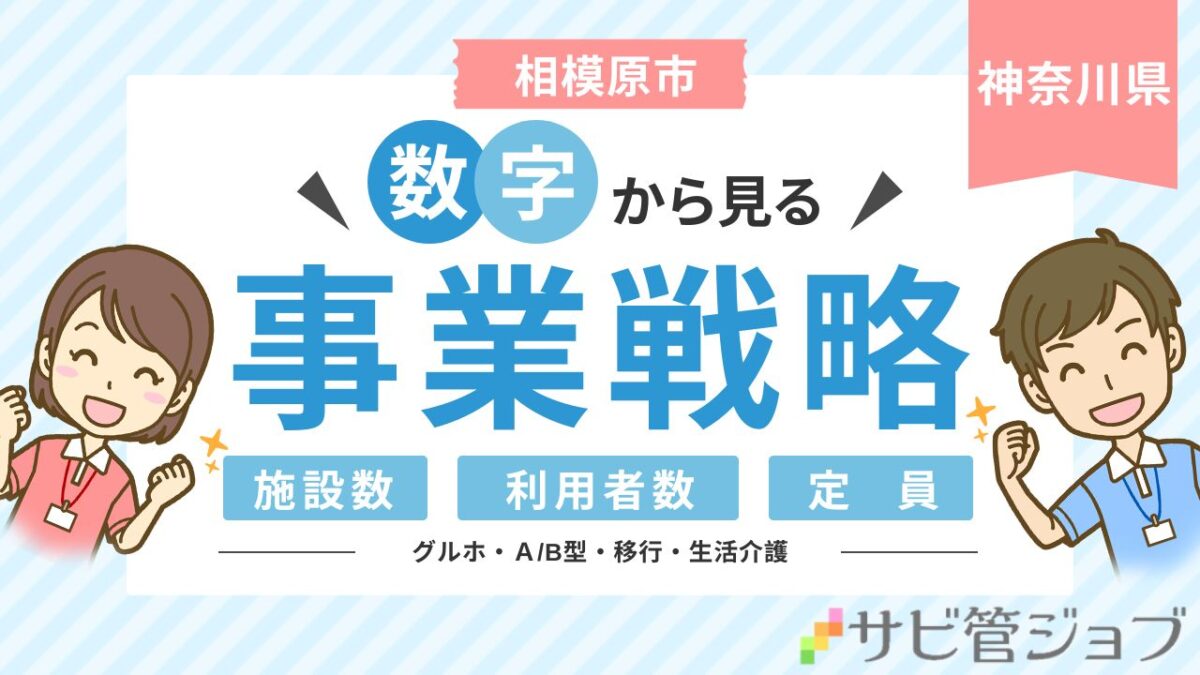相模原市(神奈川県) 障害者福祉施設の開設・運営・徹底分析ガイド|助成金・施設数・定員数 (グループホーム・就労継続支援A型/B型・就労移行支援・生活介護)
神奈川県相模原市で障害者施設の開設や運営を検討されている皆様へ。
本ガイドでは、共同生活援助(グループホーム)、就労継続支援A型・B型、就労移行支援、生活介護の立ち上げから運営、そして市場分析に至るまで、必要不可欠な情報を網羅的に解説します。
相模原市独自の助成金制度や最新の施設データも交え、実践的な指針を提供します。
相模原市 障害福祉サービスの現状と課題
神奈川県相模原市における障害者施設の安定的な運営を実現するためには、まず地域の現状を正確に把握することが不可欠です。
この章では、市の障害者人口の動向、市内に存在する障害福祉施設の数とその種類、そして実際のサービス利用状況について、最新データに基づき詳しく分析します。
これらの情報は、今後の事業計画やサービス改善の基礎となるでしょう。
相模原市の障害者人口の推移と現状
まず、相模原市の障害者人口がどのように変化しているかを見てみましょう。
以下の表は、過去5年間の障害種別ごとの人口推移を示しています。
相模原市 障害福祉サービス利用状況 (実績と見込み)
表が画面からはみ出す場合、左右にスクロールしてご覧いただけます。↔
| 障害種別 | 令和2年度 (2020年度) |
令和3年度 (2021年度) |
令和4年度 (2022年度) |
令和5年度 (2023年度) |
令和6年度 (2024年度) |
過去5年間 増減率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体障害者 | 19,660人 | 19,835人 | 19,626人 | 19,546人 | 19,523人 | -0.7% |
| 知的障害者 | 6,075人 | 6,282人 | 6,520人 | 6,810人 | 7,123人 | +17.3% |
| 精神障害者 (発達障害者を含む) |
14,964人 | 16,259人 | 16,375人 | 17,067人 | 18,259人 | +22.0% |
| 合計 | 40,699人 | 42,376人 | 42,521人 | 43,423人 | 44,905人 | +10.3% |
出典:相模原市 年度別障害児者数
相模原市が集計する障害児者数は、障害者手帳の所持状況に関わらず、市が把握する人数を基に作成されています。
多くの自治体が手帳保持者数を基準とする中で、相模原市のアプローチは手帳を持たない方々も含むため、より現実に即した数値を反映しています。
このため、他自治体との単純比較には留意が必要ですが、市内の実態に近い障害者数を捉える上で有効なデータと言えます。
表から明らかなように、相模原市の障害者総数は増加傾向にあります。
特に知的障害者と精神障害者(発達障害者を含む)の伸びが著しく、過去5年間でそれぞれ17.3%、22.0%増加しています。
これは、高齢化の進行や発達障害への認知向上などが影響していると考えられます。
施設運営においては、これらのニーズの高まりに対応できる体制整備が今後の重要な課題となるでしょう。
相模原市の障害福祉施設数とサービス種別ごとの内訳
次に、相模原市内にはどのような障害福祉施設がどれくらい存在するのか、サービス種別ごとの事業所数を確認します(令和7年(2025年)2月時点)。
相模原市 障害福祉施設数
表が画面からはみ出す場合、左右にスクロールしてご覧いただけます。↔
| 施設の種類 | 事業所数 |
|---|---|
| 共同生活援助(グループホーム) | 128事業所 |
| 就労継続支援A型 | 16事業所 |
| 就労継続支援B型 | 94事業所 |
| 就労移行支援 | 19事業所 |
| 生活介護 | 88事業所 |
市内では、グループホームが128事業所と最も多く、次いで就労継続支援B型が94事業所、生活介護が88事業所となっています。
就労継続支援A型や就労移行支援の事業所数は比較的少ない状況です。
この分布は、地域におけるサービス需要の傾向を示唆しています。
相模原市における障害福祉サービス利用状況の分析
続いて、各障害福祉サービスが実際にどの程度利用されているのか、その実績と今後の見込みを見ていきましょう。
以下の表は、サービス種別ごとの利用者数の推移(実績と見込み)を示しています。
相模原市 障害福祉サービス利用状況 (実績と見込み)
表が画面からはみ出す場合、左右にスクロールしてご覧いただけます。↔
| 施設の種類 | 令和4年度 (2022年度) (実績) |
令和5年度 (2023年度) (実績) |
令和6年度 (2024年度) (見込み) |
令和7年度 (2025年度) (見込み) |
令和8年度 (2026年度) (見込み) |
|---|---|---|---|---|---|
| 共同生活援助(グループホーム) | 1,125人 | 1,280人 | 1,457人 | 1,658人 | 1,887人 |
| 就労継続支援A型 | 243人 | 274人 | 310人 | 350人 | 395人 |
| 就労継続支援B型 | 1,408人 | 1,583人 | 1,779人 | 2,000人 | 2,249人 |
| 就労移行支援 | 262人 | 288人 | 317人 | 348人 | 383人 |
| 生活介護 | 1,742人 | 1,785人 | 1,828人 | 1,873人 | 1,919人 |
出典:第2期 共にささえあい生きる社会 さがみはら障害者プラン
※令和6年度(2024年度)以降の数値は、本記事の作成時点(令和7年(2025年)3月)では見込みであり、実績値は未公表です。
全ての主要な障害福祉サービスにおいて、利用者数は一貫して増加傾向にあり、今後もこの傾向が続くと見込まれています。
特に、グループホーム)と就労継続支援B型における利用者数の伸びが顕著であり、令和4年度(2022年度)から令和8年度(2026年度)までの4年間で、それぞれ約68%、約60%増加する見込みです。
これは、地域生活への移行支援や日中活動系のサービスに対する需要が、相模原市において引き続き高いことを示唆しています。
相模原市の障害者施設ニーズと市場を徹底分析
神奈川県相模原市で障害者施設を成功裏に運営するためには、地域のニーズと市場の動向を深く理解することが不可欠です。
この章では、各サービス種別における現在の利用者数と供給のバランス(充足状況)、さらに将来の利用者見込み数と現在の定員数を比較分析し、今後どの分野で需要が高まるかを明らかにします。
これにより、事業戦略の策定やサービス展開の方向性を定めるための重要な洞察を得ることができます。
サービス種別ごとの利用者数と充足状況(グループホーム・就労継続支援A型/B型・就労移行・生活介護)
まず、相模原市における主要な障害福祉サービスの現在の定員数に対して、どれくらいの利用が見込まれているのか、そしてそれが供給状況としてどのような評価になるのかを見ていきましょう。
以下の表は、令和6年(2024年)9月時点の定員数と、令和6年度(2024年度)から令和8年度(2026年度)までの利用者数(見込み)、さらに令和8年度(2026年度)時点での充足率と供給状況(見込み)を整理したものです。
相模原市 障害福祉サービスの充足率と供給状況
表が画面からはみ出す場合、左右にスクロールしてご覧いただけます。↔
| 障害者施設の種類 | 定員 令和6年 (2024年) 9月時点 |
利用者数(見込み) | 充足率(見込み) 令和8年度 (2026年度) |
供給状況(見込み) 令和8年度 (2026年度) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年度 (2024年度) |
令和7年度 (2025年度) |
令和8年度 (2026年度) |
||||
| 共同生活援助(グループホーム) | 1,951人 | 1,457人 | 1,658人 | 1,887人 | 97% | やや充足 |
| 就労継続支援A型 | 292人 | 310人 | 350人 | 395人 | 135% | 不足 |
| 就労継続支援B型 | 1,808人 | 1,779人 | 2,000人 | 2,249人 | 124% | 不足 |
| 就労移行支援 | 269人 | 317人 | 348人 | 383人 | 142% | 不足 |
| 生活介護 | 2,322人 | 1,828人 | 1,873人 | 1,919人 | 83% | 充足 |
出典(定員 共同生活援助以外):障害福祉サービス等情報公表システムデータのオープンデータ(令和6年(2024年)9月時点)
出典(定員 共同生活援助のみ): 障害福祉情報サービスかながわ
出典(利用者数見込み):第2期 共にささえあい生きる社会 さがみはら障害者プラン
上記出典に情報がない場合や補完が必要な場合は、他の相模原市公式資料から数値を参照しています。
これらの数値は、市に情報公開を行っている事業所のデータに基づいています。
未公開の事業所が存在する場合、実際の数値はこれより大きくなる可能性があります。
<供給状況について>
充足率(=利用者数 ÷ 定員数)に基づき、110%以上を「不足」、100%~109%を「やや不足」、90%~99%を「やや充足」、89%以下を「充足」と評価しています。
この評価は、相模原市における施設整備計画等を検討する際の参考指標となります。
上の表の通り、令和8年度(2026年度)には就労系サービスを中心に「不足」が予測され、グループホームは高い充足率が見込まれます。
各サービスの今後の需要については、次のセクションで触れていきます。
定員数と利用者見込み数から見る、今後需要が伸びるサービス種別
次に、現在の定員数(令和6年(2024年)9月時点)と、将来(令和8年度(2026年度))の利用者見込み数を比較することで、今後どのサービス種別の需要が特に伸びるのか、サービス種別ごとに詳しく見ていきましょう。
利用者見込み数は、「相模原市 障害福祉サービス利用状況(実績と見込み)」のデータ(前章参照)に基づいています。
グループホーム
共同生活援助(グループホーム)は、令和8年度(2026年度)には利用者数が1,887人に達する見込みです。
これは、令和6年(2024年)9月時点の定員1,951人に対して充足率97%に相当します。
既に定員に近い利用が見込まれており、障害者人口の増加傾向(特に知的・精神)を考慮すると、今後も安定した需要が見込まれ、さらなる供給増が求められる可能性があります。
就労継続支援A型
就労継続支援A型は、令和8年度(2026年度)の利用者見込み数が395人であるのに対し、現在の定員は292人です。
充足率は135%となり、既に「不足」が予測されています。
障害者の一般就労意欲の高まりや雇用促進策を背景に、利用者数は今後も増加すると考えられ、定員拡大や新規開設の必要性が高いサービスと言えます。
就労継続支援B型
就労継続支援B型は、令和8年度(2026年度)の利用者見込み数が2,249人と、今回分析した5つのサービスの中で最も多くなると予測されています。
現在の定員1,808人に対する充足率は124%で、「不足」が見込まれます。
多様な障害特性や就労ニーズに応えるB型事業所への需要は極めて高く、供給体制の強化が急務と考えられます。
就労移行支援
就労移行支援は、令和8年度(2026年度)の利用者見込み数が383人であるのに対し、現在の定員は269人です。
充足率は142%と、今回分析した中で最も高く、「不足」が顕著に予測されます。
一般就労を目指す障害者にとって不可欠なサービスであり、質の高い訓練と就職サポートを提供する事業所の需要は今後さらに高まるでしょう。
生活介護
生活介護は、令和8年度(2026年度)の利用者見込み数が1,919人、現在の定員は2,322人です。
充足率は83%で「充足」と評価されています。
他のサービスと比較すると供給に余裕があるように見えますが、利用者数は着実に増加しています。
特に重度化・高齢化が進む中で、医療的ケアや行動障害への対応など、専門性の高い生活介護サービスのニーズは今後も高まる可能性があります。
相模原市で障害者施設を開設する3つのメリット
神奈川県相模原市は、障害者施設の開設・運営を検討する事業者にとって、多くの魅力を持つ都市です。
ここでは、国や県の制度に加えて、相模原市ならではの利点を3つの側面から具体的に解説します。
これらのメリットを理解することは、事業計画の策定や運営戦略を考える上で役立つでしょう。
独自の補助金制度:相模原市による経済的負担軽減のための徹底解説
相模原市で障害福祉施設を運営する際に活用できる、主な補助金制度の要点をご紹介します。
これらを活用し、経済的負担の軽減を図りましょう。
-
相模原市および関連の主な補助金制度
- 相模原市障害福祉職員等キャリアアップ支援事業費補助金:
- 障害者雇用特例子会社設立支援補助金:
- 社会福祉施設等施設整備費補助金(障害福祉分野):
職員のスキルアップを目的とした研修(内部・外部)経費の一部を補助します。
補助上限は1法人あたり年15万円です。
障害者雇用を目的とする特例子会社を設立する際の、初期整備費用の一部を補助します。
補助上限は500万円です。
国庫補助金を活用し、障害福祉施設の新設や改修等にかかる費用を補助する制度です。
相模原市が政令指定都市のため、申請窓口や実施主体は原則として相模原市になります。
ここで紹介した補助金制度は主な例です。
内容は変更されることや、対象要件、申請期間が定められている場合があります。
ご利用を検討される際は、最新の情報を相模原市の公式ウェブサイトや担当窓口にて直接ご確認ください。
交通アクセスの利便性と都市機能:都心へのアクセスと充実した都市機能の両立
相模原市は、東京都心や横浜方面へのアクセスが非常に良好な点が大きな特徴です。
JR横浜線、小田急線、京王相模原線などが市内を走り、例えば橋本駅から新宿駅へは約40分、横浜駅へも約40分程度でアクセス可能です。
この利便性は、広範囲からの職員の通勤を容易にし、人材確保の面で有利に働きます。
また、利用者の家族が面会に訪れやすいというメリットもあります。
相模原市はJR横浜線・小田急線・京王線で都心や横浜へ約40分とアクセス抜群で、職員の通勤や家族の面会に便利です。
将来的なリニア中央新幹線駅(橋本)の設置計画も控えています。
加えて、相模大野・橋本駅周辺などの商業施設や、北里大学病院・相模原協同病院といった大規模病院も市内に充実。
交通利便性と都市機能を兼ね備え、安心して施設運営ができる環境が整っています。
広大な敷地と豊かな自然環境:緑豊かな環境を活かした施設運営
相模原市は、政令指定都市でありながら、都心部に比べて比較的広い土地を確保しやすいという、施設運営にとって魅力的な側面を持っています。
特に緑区などでは、豊かな自然環境が残されており、これを活かした特色ある施設運営が可能です。
例えば、以下のような、相模原市の地理的特性を活かした施設展開が考えられます。
-
相模原市の自然・環境を活かした運営例
- 敷地内での農園芸活動:
- 近隣の自然資源の活用:
- 落ち着いた環境での療育・支援:
確保した敷地内に畑や花壇を作り、利用者が野菜や草花を育てるプログラムを導入。
土に触れる活動は心身のリフレッシュや達成感につながります。
相模川の河川敷、相模原麻溝公園、相模原公園、津久井湖周辺など、市内に点在する広大な公園や自然スポットを活用した外出レクリエーションやウォーキングプログラムを企画。
四季の移ろいを感じられる活動は利用者のQOL向上に寄与します。
都心の喧騒から離れた、緑が多く静かな環境は、感覚過敏のある利用者や落ち着いた環境を必要とする利用者にとって、安心して過ごせる場を提供します。
相模原市の豊かな自然環境は、利用者のQOL(生活の質)向上と、職員にとって働きやすい職場環境の提供に繋がります。
これは職員の定着を促進し、ひいては質の高いサービスの継続や経営の安定化に貢献する、相模原市ならではの大きな付加価値となるでしょう。
相模原市の主要な連携機関:施設開設・運営を支える強力なネットワーク
障害者施設の円滑な開設と質の高い運営を実現するためには、地域社会に根差した多様な機関との連携が不可欠です。
神奈川県相模原市には、行政から医療、教育、地域団体まで、施設運営を力強くサポートするネットワークが存在します。
この章では、特に重要となる連携先を具体的に紹介し、それぞれの機関とどのように協力関係を築いていくべきか解説します。
行政機関(市役所・関連部署)
施設開設の許認可申請、補助金の相談、運営基準の確認など、事業の根幹に関わる手続きや相談に対応するのが行政機関です。
相模原市においては、以下の部署が主要な窓口となります。
-
相模原市役所の主な担当部署
- 障害福祉課 (市役所本庁舎):
- 各区役所 高齢・障害者相談課 (緑区・中央区・南区):
障害福祉サービス事業所の指定申請・変更届、補助金に関する手続き、運営指導などを所管する中心的な部署です。
開設準備段階から運営に関する専門的な相談まで、幅広く対応しています。
(代表電話経由での問い合わせが一般的です。
相模原市ウェブサイト等でご確認ください。
)
地域住民からの障害福祉に関する相談の第一線窓口であり、地域の相談支援事業所や民生委員などとの連携を担っています。
施設が所在する区の担当課と日頃から情報交換を行うことで、地域ニーズの把握や利用者紹介に繋がる可能性があります。
これらの行政機関とは、法令遵守はもちろん、地域の障害福祉施策の動向を把握するためにも、密接な連携を保つことが重要です。
相談支援事業所
相談支援事業所は、障害のある方々が適切なサービスを利用できるよう、サービス等利用計画の作成や関係機関との連絡調整を行う専門機関です。
施設運営者にとっては、利用者の紹介や受け入れ調整、個別支援計画作成における情報共有など、日常的な連携が欠かせないパートナーとなります。
-
相模原市における相談支援体制
- 相模原市基幹相談支援センター:
- 各地域の指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所:
市内全域を対象とし、地域の相談支援事業者への支援や、困難事例への対応、権利擁護に関する取り組みなどを行う中核的な役割を担っています。
事業者向けの研修会などを開催することもあります。
利用者の計画作成を担う地域の相談支援事業所は、基幹相談支援センターが全体調整を行う相模原市の体制のもと、各区で活動しています。
施設運営においては、特に相模原市で増加している知的・精神障害への対応実績や、自施設の専門性を考慮し、適切な事業所と日頃から顔の見える関係を築き、情報連携を密にすることが成功の鍵となります。
医療機関(病院・クリニック)
利用者の健康管理、急病や事故発生時の緊急対応、医療的ケアが必要な方への対応など、医療機関との連携は施設運営の生命線とも言えます。
相模原市内には、高度な医療を提供する基幹病院から、地域に密着したクリニックまで、多様な医療機関が存在します。
-
相模原市内の主要な連携先候補(例)
- 北里大学病院(南区):
- 相模原協同病院(緑区):
- 地域のクリニック・診療所:
- 精神科医療機関:
特定機能病院として高度・専門的な医療を提供しています。
多様な診療科を有し、難病や合併症を持つ利用者の対応などで連携が考えられます。
地域医療支援病院として、救急医療を含む幅広い医療を提供しています。
地域の基幹病院として日常的な健康管理から緊急時対応まで連携が重要です。
また、同院は地域医療連携ネットワークを運用しており、参加施設間で診療情報の共有を行っています。
日常的な健康相談や定期的な受診、往診などで連携が可能です。
利用者の状況や施設の立地に合わせて、協力関係を築ける「かかりつけ医」を見つけることが望ましいです。
精神障害のある利用者が多い場合、専門的な精神科医療を提供する病院との連携体制を構築しておくことが、適切なケアとリスク管理に繋がります。
相模原市周辺では神奈川県立精神医療センター(厚木市)などが候補です。
利用者の状態やニーズに合わせて、平時からの情報共有や緊急時の受け入れ体制について、具体的な連携方法を協議しておくことが重要です。
教育機関(特別支援学校・大学等)
地域の教育機関との連携は、人材育成や地域貢献、利用者の社会参加の促進など、多方面にメリットをもたらします。
相模原市内には、障害のある児童生徒が通う特別支援学校や、福祉・医療系の専門職を養成する大学・専門学校があります。
-
相模原市内の連携候補となる教育機関(例)
- 神奈川県立相模原中央支援学校:
- 神奈川県立相模原支援学校:
- 神奈川県立津久井支援学校:
- 相模女子大学(南区):
- 和泉短期大学(中央区):
- 医療ビジネス観光福祉専門学校(南区):
視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由のある児童生徒を対象としています。
職場体験実習の受け入れや進路相談、地域移行支援での連携が有効です。
知的障害のある児童生徒が通う特別支援学校です。
卒業後の地域移行支援や日常生活支援の情報共有などが連携のポイントとなります。
知的障害および肢体不自由のある児童生徒を対象としています。
卒業後の進路支援や地域での生活支援で協力が期待できます。
福祉や心理の専門職を養成しており、実習生の受け入れによる人材育成や、共同研究・研修会の開催等で連携できます。
介護福祉士養成課程を持つ短期大学です。
介護・福祉分野の人材育成で連携が図れます。
福祉関連の専門職を養成しています。
実習生の受け入れや施設での実践的な教育を通じて、相互にメリットのある連携が可能です。
これらの教育機関と連携することで、施設運営の質を高め、人材確保や地域貢献にも繋げられます。
日頃から情報共有や具体的な連携方法について調整しておくことが重要です。
その他の関連機関・団体(社会福祉協議会等)
行政、医療、教育以外にも、地域には施設運営を支える様々な団体が存在します。
これらの機関との連携により、地域資源の活用やネットワークの拡大が期待できます。
-
相模原市内の主要な関連機関・団体(例)
- 相模原市社会福祉協議会(社協):
- NPO法人れんきょう(相模原市障害児者福祉団体連絡協議会):
- 相模原市身体障害者連合会:
- 地域のNPO法人・ボランティア団体:
地域福祉の中核を担う組織として、ボランティアセンターの運営、地域活動への助成、福祉情報の提供を行っています。
施設でのボランティア受け入れや地域交流イベントの共同開催など、積極的な連携が可能です。
市内の障がい児・障がい者福祉団体が加盟する協議会です。
障がい当事者のニーズや意見を行政に届けるほか、各種行事や研修会、情報発信を行っており、当事者の視点を理解する上で重要な連携先となります。
市内の身体障害者団体が加盟し、障害者福祉の向上を目指して活動しています。
啓発活動や講演会、イベント開催などを通じて連携が可能であり、障害理解の促進にも繋がります。
市内のNPO・ボランティア団体との連携は、専門プログラム導入や地域交流の促進に有効です。
相模原市社会福祉協議会のボランティアセンター等で情報収集を行い、自施設のニーズに合った団体との協働を検討しましょう。
これらの多様な機関・団体と積極的に関わり、情報交換や協力体制を構築していくことが、地域に開かれ、信頼される施設運営の鍵となります。
【掲載無料】「貴施設の魅力を、相模原市の利用者様へ届けませんか?」
概要
日々の施設運営、誠にお疲れ様です。
当サイトでは、当記事とは別に、相模原市の障害者の利用者様やそのご家族に向けたお役立ち記事を運営しております。
つきましては、その記事内で「相模原市のおすすめ施設」として、貴施設の活動を完全無料でご紹介したく、ご協力くださる事業所様を募集しております。
未来の利用者様へ貴施設の魅力を直接アピールできる絶好の機会です。
なお、記事の品質と情報量を適切に保つため、ご紹介できる施設様の数には限りがございます。
続きを読む
費用
費用は一切かかりません。
掲載
ページ
掲載場所につきましては、記事内の下部、まとめ見出しの直上の位置を予定しております。
お願い
当サイトでは、読者の皆様に信頼性の高い情報をお届けすることを何よりも大切にしております。
そのため、掲載させていただくにあたり、施設の公式サイトを運営されていることや、情報が確認できることなど、
いくつか簡単なお願いをさせていただく場合がございます。
ご応募
ご興味のある施設様は、お手数ですが、下記の情報をご記入の上、専用のお問い合わせページよりご連絡ください。
担当者より、折り返し詳細をご案内させていただきます。
まとめ
本記事では、神奈川県相模原市における障害者施設(グループホーム、就労継続支援A型/B型、就労移行支援、生活介護)の開設・運営に焦点を当て、現状分析から具体的なメリット、連携体制までを解説してきました。
最後に、重要なポイントを簡潔にまとめます。
-
相模原市での施設運営:要点まとめ
- 高まる需要:
- 市の手厚い支援:
- 優れたアクセスと環境:
- 多様な連携先:
障害者人口、特に知的・精神障害者層が増加。
グループホームや就労継続支援B型を中心にサービス利用が伸びており、将来的に生活介護を除く多くのサービスで供給不足(特に就労系)が予測されます。
施設整備費や運営費に対する市独自の補助金、過去の物価高騰対策給付金など、経営を支える経済的支援が期待できます。
都心への良好な交通網(リニア計画含む)、充実した都市機能、そして比較的確保しやすい敷地と豊かな自然環境が両立しています。
市役所(障害福祉課・区役所)、基幹相談支援センター、北里大学病院・相模原協同病院、特別支援学校、社会福祉協議会など、具体的な連携機関との関係構築が不可欠です。
相模原市は、障害福祉サービスの需要が高まる一方で、事業者にとって魅力的な環境と支援体制を提供しています。
本ガイドで得られた情報を活用し、地域のニーズに応え、質の高いサービスを提供する施設運営を、ぜひ相模原市で実現してください。