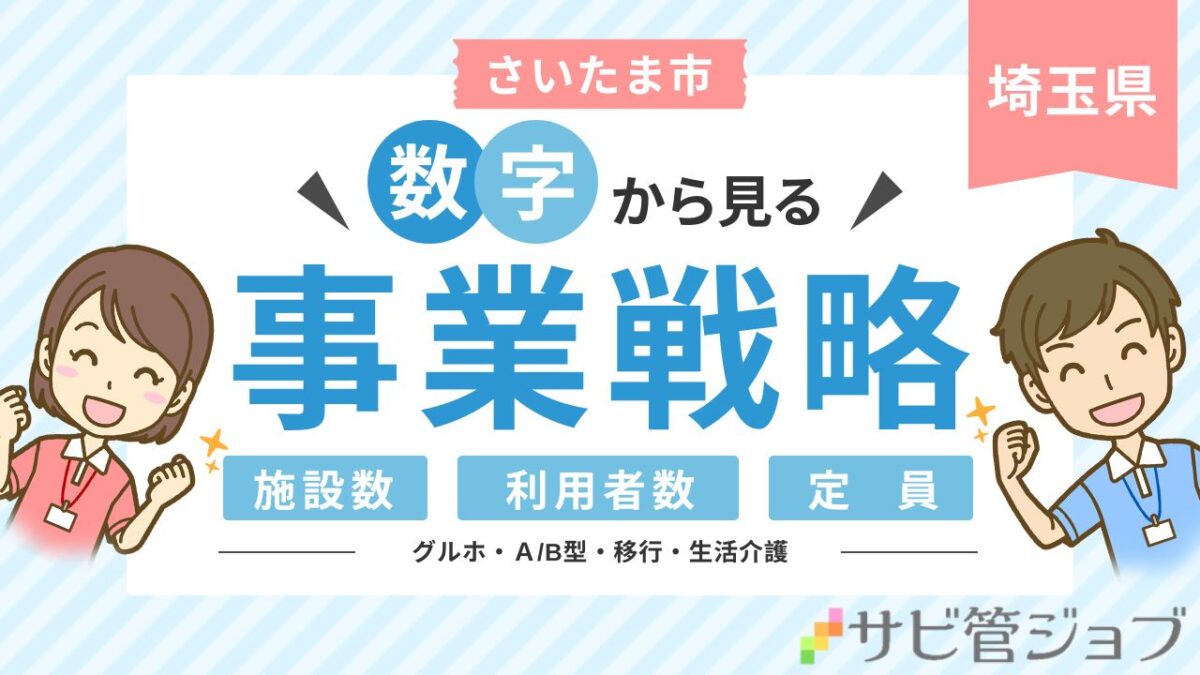さいたま市(埼玉県) 障害者福祉施設の開設・運営・分析ガイド|助成金・施設数・定員数 (グループホーム・就労継続支援A型/B型・就労移行支援・生活介護)
本記事では、埼玉県さいたま市で障害者福祉施設の開設・運営を検討されている方に向けて、市の現状、ニーズ、市場分析、開設のメリット、主要な連携機関などを徹底的に解説します。
さいたま市独自の助成金情報や、今後の需要予測なども盛り込み、施設運営を成功させるためのヒントを提供します。
さいたま市 障害福祉サービスの実態と現状を把握する
埼玉県さいたま市における障害福祉サービスの現状を把握するためには、障害者人口の推移、障害福祉施設数、サービス利用状況の3つの視点から分析することが重要です。
ここでは、それぞれのデータに基づき、さいたま市の障害福祉サービスの実態を詳しく解説します。
これらの情報を確認し、今後の施設運営の参考にしてください。
さいたま市の障害者人口と推移 (障害者手帳所持者数の把握)
さいたま市の障害者人口の推移を把握することは、今後の障害福祉サービスに対する需要を予測するために不可欠です。
下記の表では、令和元年(2019年)から令和5年(2023年)までの障害者手帳所持者数を示しています。
さいたま市 障害福祉サービス利用状況 (実績と見込み)
表が画面からはみ出す場合、左右にスクロールしてご覧いただけます。↔
| 障害者の種類 | 令和元年 (2019年) |
令和2年 (2020年) |
令和3年 (2021年) |
令和4年 (2022年) |
令和5年 (2023年) |
過去5年間増減率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体障害者手帳 (対象:身体障害者) |
33,293人 | 33,497人 | 33,430人 | 33,447人 | 33,274人 | -0.1% |
| 療育手帳 (対象:知的障害者) |
7,768人 | 8,023人 | 8,339人 | 8,638人 | 9,045人 | +16.4% |
| 精神障害者保健福祉手帳 (対象:精神/発達障害者) |
11,756人 | 12,776人 | 13,643人 | 14,592人 | 15,708人 | +33.6% |
| 合計 | 52,817人 | 54,296人 | 55,412人 | 56,677人 | 58,027人 | +9.9% |
出典:さいたま市 障害者総合支援計画 2024 ~ 2026(令和6 ~ 8年度)
この表から、さいたま市では精神障害者保健福祉手帳の所持者数が過去5年間で33.6%増加しており、知的障害者の方も16.4%増と大幅な増加傾向にあることがわかります。
一方、身体障害者手帳の所持者数はほぼ横ばいです。
これらのデータから、精神障害や知的障害を持つ方への支援ニーズが特に高まっていると考えられます。
さいたま市の障害福祉施設数とサービス種別ごとの内訳
次に、さいたま市内の障害福祉施設数をサービス種別ごとに見ていきましょう。
これにより、どのような種類の施設がどの程度存在するかを把握できます。
さいたま市 障害福祉施設数
表が画面からはみ出す場合、左右にスクロールしてご覧いただけます。↔
| 施設の種類 | 事業所数 |
|---|---|
| グループホーム | 210事業所 |
| 就労継続支援A型 | 29事業所 |
| 就労継続支援B型 | 107事業所 |
| 就労移行支援 | 48事業所 |
| 生活介護 | 82事業所 |
出典:障害福祉サービス等情報公表システムデータのオープンデータ(令和6年(2024年)9月時点)
この表から、さいたま市ではグループホーム(共同生活援助)の事業所数が最も多く、次いで就労継続支援B型、生活介護の事業所数が多いことがわかります。
これらのデータは、各サービス種別ごとの供給状況を把握する上で重要な指標となります。
さいたま市における障害福祉サービスの利用状況
最後に、さいたま市における障害福祉サービスの利用状況(実績と見込み)を見てみましょう。
これにより、各サービスがどの程度利用されているのか、今後の需要はどうなるのかを予測することができます。
さいたま市 障害福祉サービス利用状況 (実績と見込み)
表が画面からはみ出す場合、左右にスクロールしてご覧いただけます。↔
| 施設の種類 | 令和4年 (2022年) (実績) |
令和5年 (2023年) (実績) |
令和6年 (2024年) (見込み) |
令和7年 (2025年) (見込み) |
令和8年 (2026年) (見込み) |
|---|---|---|---|---|---|
| グループホーム | 947人 | 1,100人 | 1,245人 | 1,427人 | 1,636人 |
| 就労継続支援A型 | 540人 | 903人 | 513人 | 500人 | 487人 |
| 就労継続支援B型 | 1,774人 | 1,792人 | 2,228人 | 2,497人 | 2,798人 |
| 就労移行支援 | 506人 | 453人 | 546人 | 568人 | 590人 |
| 生活介護 | 2,071人 | 2,244人 | 2,156人 | 2,199人 | 2,243人 |
出典:さいたま市 障害者総合支援計画 2024 ~ 2026(令和6 ~ 8年度)
※令和6年度(2024年度)以降の実績は記事投稿時(2025年3月時点)でまだ公開されてないため見込みとなります。
この表から、グループホーム(共同生活援助)と就労継続支援B型の利用者数が大幅に増加する見込みであることがわかります。
一方、就労継続支援A型は令和5年(2023年)に利用者が急増していますが、その後は減少傾向にある点に注意が必要です。
これらのデータは、今後の施設整備計画やサービス提供体制を検討する上で非常に重要な情報となります。
さいたま市の障害者施設におけるニーズと市場を徹底分析
さいたま市で障害者施設を開設・運営するにあたり、利用者ニーズと市場動向を正確に把握することは、事業の成功を左右する重要な要素です。
ここでは、各障害福祉サービス種別の利用者数の現状と過不足を検証し、今後の需要予測について詳しく解説します。
これらのデータを参考に、適切な事業計画を立て、利用者ニーズに応えられる施設運営を目指しましょう。
障害者施設のサービス種別ごとの利用者数の現状と過不足を検証する (グループホーム・就労継続支援A型/B型・就労移行支援・生活介護)
さいたま市における障害福祉サービスの供給状況を把握するために、各サービス種別の定員、利用者数、充足率、供給状況をまとめたものが以下の表です。
さいたま市 障害福祉サービスの充足率と供給状況
表が画面からはみ出す場合、左右にスクロールしてご覧いただけます。↔
| 障害者施設の種類 | 定員 令和6年 (2024年)9月時点 |
利用者数(見込み) 令和6年 (2024年) |
利用者数(見込み) 令和7年 (2025年) |
利用者数(見込み) 令和8年 (2026年) |
充足率(見込み) 令和8年 (2026年) |
供給状況(見込み) 令和8年 (2026年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グループホーム | 1,432人 | 1,245人 | 1,427人 | 1,636人 | 114% | 不足 |
| 就労継続支援A型 | 565人 | 513人 | 500人 | 487人 | 86% | 充足 |
| 就労継続支援B型 | 2,101人 | 2,228人 | 2,497人 | 2,798人 | 133% | 不足 |
| 就労移行支援 | 810人 | 546人 | 568人 | 590人 | 73% | 充足 |
| 生活介護 | 2,173人 | 2,156人 | 2,199人 | 2,243人 | 103% | やや不足 |
出典:)障害福祉サービス等情報公表システムデータのオープンデータ(令和6年(2024年)9月時点
出典:さいたま市 障害福祉施設等一覧 令和6年4月1日時点 (グループホームの定員のみ)
※上記の出典元に掲載されていない場合、その他市町村の公式資料の数値を反映させております。
本数値は、市町村に情報を公開している事業所のデータに基づいており、情報を公開していない事業所がある場合は、数値が増加する可能性がございます。
<供給状況について>
充足率は定員に対する利用者の割合です。
110%以上は「不足」、100%~109%は「やや不足」、90%~99%は「やや充足」、89%以下は「充足」と評価しています。
この充足率は、さいたま市における施設整備やサービス提供計画を検討する上での参考指標としてご活用ください。
この表から、令和8年(2026年)には、グループホーム(共同生活援助)と就労継続支援B型は「不足」、生活介護は「やや不足」となる見込みです。
一方、就労継続支援A型と就労移行支援は「充足」となる見込みです。
これらのデータから、さいたま市では特にグループホームと就労継続支援B型のニーズが高いことがわかります。
利用者数の見込みと施設の定員数から、今後需要増加が見込まれる施設の種類を予測する
ここでは、前述の表で示した利用者数の見込みと施設の定員数から、今後、さいたま市で需要増加が見込まれる障害者施設の種類を予測します。
グループホーム(共同生活援助)
令和6年(2024年)9月時点の定員1,432人に対し、令和8年(2026年)の見込み利用者数は1,636人と、定員を大きく上回る予測となっています。
充足率は114%で「不足」と評価されており、今後も需要増加が見込まれるため、新規開設の余地が十分にあると考えられます。
就労継続支援A型
令和6年(2024年)9月時点の定員565人に対し、令和8年(2026年)の見込み利用者数は487人と、定員を下回る予測となっています。
充足率は86%で「充足」と評価されており、現状では施設の供給が需要を上回っている状況です。
しかし、利用者の就労状況やニーズの変化によっては、今後状況が変わる可能性もありますので、引き続き動向を注視していく必要があります。
就労継続支援B型
令和6年(2024年)9月時点の定員2,101人に対し、令和8年(2026年)の見込み利用者数は2,798人と、定員を大幅に上回る予測となっています。
充足率は133%で「不足」と評価されており、今後も需要増加が見込まれるため、新規開設の余地が十分にあると考えられます。
就労移行支援
令和6年(2024年)9月時点の定員810人に対し、令和8年(2026年)の見込み利用者数は590人と、定員を下回る予測となっています。
充足率は73%で「充足」と評価されており、現状では施設の供給が需要を上回っている状況です。
しかし、就労支援のニーズは多様化しているため、利用者の状況やニーズの変化によっては、今後状況が変わる可能性もありますので、引き続き動向を注視していく必要があります。
生活介護
令和6年(2024年)9月時点の定員2,173人に対し、令和8年(2026年)の見込み利用者数は2,243人と、定員をわずかに上回る予測となっています。
充足率は103%で「やや不足」と評価されています。
生活介護は、比較的重度の障害を持つ方が利用するサービスであるため、大幅な需要増は見込みにくいですが、一定のニーズは継続すると考えられます。
さいたま市で障害者施設を開設する3つのメリット
埼玉県さいたま市で障害者施設を開設することは、事業者にとって多くのメリットがあります。
ここでは、さいたま市ならではの3つのメリットに焦点を当て、詳しく解説します。
これらの情報を参考に、さいたま市での施設開設を検討してみてはいかがでしょうか。
さいたま市独自の補助金・助成金制度をご紹介
さいたま市では、障害者福祉施設の安定的な運営とサービス向上を支援するため、独自の補助金制度を設けています。
これらの補助金を活用することで、施設運営における経済的な負担を軽減することができます。
ここでは、さいたま市が提供する主な補助金について、その概要とポイントを解説します。
-
さいたま市の主な補助金
- 社会福祉施設職員キャリアアップ支援事業補助金:
- 社会福祉施設等施設整備費国庫補助金:
- さいたま市共同生活援助運営費補助金:
- グループホーム運営費補助事業 補助金:
社会福祉施設職員の資質向上を目的とした研修受講費・資格取得費用の補助金です。
介護福祉士等の資格取得や、実務者研修、喀痰吸引等研修の受講料が対象です。
出典:さいたま市社会福祉施設職員キャリアアップ支援事業補助金交付要綱
社会福祉施設の創設・増築・大規模修繕等の費用を国が補助する制度で、さいたま市を経由して申請します。
障害者支援施設、グループホーム(共同生活援助)、就労支援施設などが対象です。
出典:社会福祉施設等施設整備費に係る国庫補助協議について
さいたま市が実施主体となり、グループホームの運営費(家賃、光熱水費、利用者負担軽減額、人件費等)を補助します。
国の制度に基づく都道府県補助金を経て交付されます。
出典:さいたま市共同生活援助運営費補助金交付要綱
さいたま市独自の補助金で、グループホームの運営費を補助します。
「さいたま市共同生活援助運営費補助金」に上乗せして利用可能です。
出典:グループホーム運営費補助事業の概要
これらの補助金は、それぞれ申請期間や要件が異なります。
最新の情報を確認し、計画的に申請手続きを進めることが重要です。
また、不明な点がある場合は、さいたま市の担当窓口に相談することをおすすめします。
大宮駅を中心とした交通網を活用した広域利用の可能性
さいたま市は、特に大宮駅が東北・上越・北陸新幹線を含むJR各線、東武野田線、埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル)など、多くの路線が乗り入れる巨大ターミナル駅となっています。
この大宮駅を中心に広がる交通網を活用することで、埼玉県内だけでなく、首都圏全域、さらには北関東や甲信越地方からの広域利用を促進できます。
具体的には、以下のような広域利用促進策が考えられます。
-
広域利用促進策
- 新幹線停車駅の強みを活かした情報発信:
- 近隣都県との連携:
- 鉄道会社との連携:
- バリアフリー情報の充実:
大宮駅が新幹線の停車駅であることを積極的にアピールし、遠方からの利用者にもアクセスしやすいことを周知します。
群馬県、栃木県、茨城県など、北関東の近隣都県と連携し、共同での広報活動や情報交換を行います。
JR東日本や東武鉄道などの鉄道会社と連携し、お得な乗車券や周遊パスの開発、駅構内での情報提供などを検討します。
大宮駅構内や周辺施設のバリアフリー情報を詳細に提供し、障害のある方が安心して利用できる環境を整えます。
(例:エレベーターの位置、多目的トイレの有無、スロープの設置状況など)
これらの施策により、さいたま市の障害者施設は、より広範囲な利用者ニーズに応えることができるのではないでしょうか。
将来的な人口増加と障害福祉サービス需要の拡大
さいたま市は、都心へのアクセスが良く、子育て支援も充実していることから、住みやすい街として人気があり、人口増加とともに障害福祉サービスの需要も高まっています。
その魅力を以下の3つのポイントにまとめました。
-
さいたま市の魅力と将来性
- 住みやすい街として高評価:
- 人口増加傾向:
- 障害福祉サービス需要の増加見込み:
SUUMO「2024年 首都圏版住みたい街ランキング」で大宮が2位、浦和が10位にランクイン。
その他様々な調査機関のランキングでも上位に位置しており、住みやすい街として広く認知されています。
さいたま市の人口は令和2年(2020年)1月の1,309,768人から令和7年(2025年)1月には1,351,535人へと、5年間で約3.2%増加しています。
(出典:埼玉県推計人口(月報データ))
これは、同時期の全国平均の人口増加率を上回る数値です。
さいたま市の「さいたま市 障害者総合支援計画」によると、今後も障害福祉サービスの需要は増加していく見込みです。
市では、この計画に基づき、更なるサービス基盤の整備を進める方針です。
(出典:さいたま市 障害者総合支援計画 2024 ~ 2026(令和6 ~ 8年度))
住みやすい街として人気が高く、人口増加と障害福祉サービス需要の拡大が見込まれるさいたま市は、障害者施設運営に最適な環境です。
市の充実した支援策も活用しながら、地域社会に貢献できる施設づくりを、ぜひご検討ください。
さいたま市の主要連携機関:開設・運営をサポートするネットワーク
埼玉県さいたま市で障害者施設を開設・運営する際には、さまざまな関係機関との連携が不可欠です。
ここでは、さいたま市における主要な連携機関を5つのカテゴリに分けて紹介します。
これらの機関とのネットワークを構築することで、円滑な施設運営をサポートし、利用者へのより質の高いサービス提供につなげることができます。
行政機関
さいたま市の行政機関は、障害者施設の開設・運営に関するさまざまなサポートを提供しています。
主な窓口としては、以下の部署が挙げられます。
-
主な行政機関
- さいたま市 保健福祉局 障害部 障害福祉課:
- 各区役所 支援課:
- さいたま市 障害者更生相談センター:
障害福祉サービス全般に関する相談、申請手続き、情報提供などを行います。
区内の障害者福祉に関する相談窓口として、身近な相談に対応します。
専門的な相談支援や、補装具の判定などを行います。
これらの行政機関は、施設の開設準備段階から運営段階まで、さまざまな場面でサポートを提供してくれます。
積極的に活用しましょう。
相談支援事業所
相談支援事業所は、障害のある方やその家族からの相談に応じ、必要な情報提供や助言、関係機関との連絡調整などを行う機関です。
さいたま市内には、さまざまな相談支援事業所があります。
-
相談支援事業所の種類
- 指定特定相談支援事業所:
- 指定一般相談支援事業所:
- 指定障害児相談支援事業所:
サービス等利用計画の作成や、関係機関との連絡調整などを行います。
地域移行支援や地域定着支援などを行います。
障害児通所支援の利用計画作成などを行います。
これらの相談支援事業所と連携することで、利用者への適切なサービス提供や、地域資源の有効活用につなげることができます。
医療機関
障害のある方の中には、医療的なケアを必要とする方もいます。
さいたま市内には、障害者医療に力を入れている病院やクリニックが多数あり、これらの医療機関との連携は、利用者の健康管理や緊急時の対応に不可欠です。
例えば、埼玉医科大学病院(総合)、埼玉県総合リハビリテーションセンター、埼玉県立精神医療センターなど、専門性の高い医療機関との連携が可能です。
また、埼玉県が推進する「埼玉県地域医療連携推進事業」により、地域の医療機関との連携体制も整っており、施設利用者の状態に応じた適切な医療機関への紹介や情報共有がスムーズに行えます。
-
連携が考えられる医療機関の例
- 総合病院:
- 精神科病院・クリニック:
- リハビリテーション科のある病院・クリニック:
- 訪問診療を行うクリニック:
専門的な診療科や高度な医療設備を備えており、さまざまな疾患に対応できます。
(例:埼玉医科大学病院、さいたま市立病院、自治医科大学附属さいたま医療センターなど)
精神疾患を持つ利用者への専門的なケアを提供します。
(例:埼玉県立精神医療センター、さいたま市内の各精神科クリニックなど)
機能訓練やリハビリテーションを提供します。
(例:埼玉県総合リハビリテーションセンター、さいたま市内のリハビリテーション科のある病院・クリニックなど)
施設への訪問診療に対応しているクリニックもあります。
さいたま市の「医療機関情報」や厚生労働省の「医療機能情報提供制度」で、訪問診療を行っているクリニックを検索できます。
また、かかりつけ医がいる場合は、訪問診療が可能かどうか相談してみましょう。
利用者の状況に応じて、適切な医療機関との連携体制を構築しましょう。
さいたま市保健福祉局や、各区の支援課に相談することで、連携可能な医療機関の紹介を受けることも可能です。
教育機関
特に、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの児童を対象としたサービスを提供する場合は、地域の教育機関との連携が重要になります。
さいたま市内には、特別支援学校や小学校、中学校など、さまざまな教育機関があり、それぞれ特色ある教育活動を展開しています。
-
連携が考えられる教育機関の例
- 特別支援学校:
- 小学校・中学校:
- 高等学校:
専門的な知識やノウハウを持つ教員がおり、情報交換や連携が可能です。
例えば、さいたま市立大宮特別支援学校では、地域との交流活動に力を入れており、近隣の小学校との交流会などを実施しています。
通常の学級に通う発達障害のある児童生徒への支援について、さいたま市内の小学校・中学校と連携できます。
さいたま市では、全ての子どもたちが共に学ぶ教育を推進しており、各学校で通級指導教室の設置、特別支援教育コーディネーターや専門家チームの配置など、様々な取り組みが行われています。
卒業後の進路に関する情報交換や連携が可能です。
さいたま市内には、埼玉県立高等学園のように、職業学科を設置し、障害のある生徒の就労支援に力を入れている学校もあります。
さいたま市では、さいたま市教育委員会が中心となり、各学校と連携して、全ての子どもたちが共に学び、成長できる教育環境づくりに取り組んでいます。
その他の関連機関・団体
さいたま市には、障害者施設運営をサポートするさまざまな関連機関・団体があります。
これらの機関・団体は、さいたま市の掲げる「共生社会の実現」に向け、重要な役割を担っています。
-
その他の関連機関・団体
- さいたま市社会福祉協議会:
- 障害者就業・生活支援センター:
- ハローワーク:
- NPO法人、一般社団法人など:
福祉サービスに関する相談や情報提供、ボランティアの育成などを行います。
さいたま市内には複数のセンターがあり、就労に関する相談や支援、職場開拓などを行います。
(例:さいたま市障害者就業・生活支援センター)
求職活動の支援や、障害者雇用の相談などを行います。
(例:ハローワーク浦和、ハローワーク大宮など)
さいたま市内では、障害者支援に関するさまざまな活動を行っている団体があります。
例えば、特定非営利活動法人埼玉県障害者協議会は、障害者の権利擁護や社会参加促進に関する活動を行っています。
これらの機関・団体とのネットワークを構築することで、より幅広い視点から施設運営をサポートし、利用者へのより質の高いサービス提供につなげることができます。
さいたま市では、関係機関・団体との連携を重視しており、情報交換や研修会などを通じて、相互理解を深めるための取り組みも行われています。
まとめ
本記事では、埼玉県さいたま市における障害者福祉施設の開設・運営について、現状分析、ニーズと市場予測、開設のメリット、主要な連携機関という4つの視点から解説しました。
以下に、記事のポイントをまとめます。
-
さいたま市 障害者施設 開設・運営のポイント
- 現状把握:
- ニーズと市場:
- 開設メリット:
- 連携機関:
さいたま市の障害者人口は増加傾向にあり、特に精神障害者保健福祉手帳所持者、および療育手帳所持者の増加が顕著です。
施設数はグループホーム(共同生活援助)、就労継続支援B型が多い状況ですが、利用者数の見込みが定員を大幅に上回り、「不足」状態。
生活介護も「やや不足」であり、これらのサービスを提供する施設の需要が高いです。
さいたま市独自の補助金制度、交通利便性の高さ、多様なニーズに応える地域包括ケアシステムの進展が、施設開設の大きなメリットとなります。
行政機関、相談支援事業所、医療機関、教育機関、その他の関連団体との連携が、円滑な施設運営と質の高いサービス提供に不可欠です。
これらの情報を総合的に検討し、さいたま市の特性を活かし、障害者施設開設・運営を成功させ、地域社会に貢献していきましょう。
本記事が、その一助となれば幸いです。