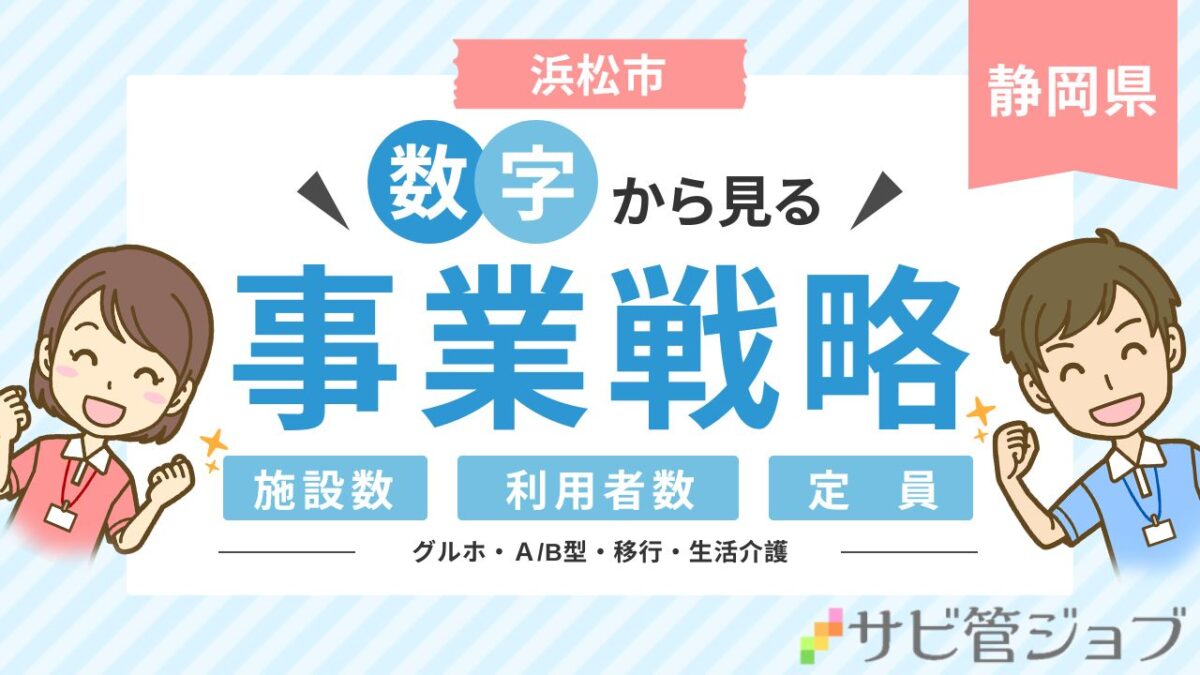浜松市(静岡県) 障害者施設 立ち上げ・運営・分析ガイド|補助金・施設数・定員(グルホ・A型B型・就労移行・生活介護)
静岡県浜松市における障害者施設の運営を検討している方へ向けて、補助金制度や施設数、定員状況をわかりやすくまとめたガイドです。
本記事では、障害者施設の開設・運営に役立つ最新動向や実績データをもとに、施設種別ごとの需要や地域特性を分析しています。
🌟施設運営者の皆さまへ
「サービス管理責任者」の採用に
お困りではありませんか?
サビ管ジョブは、サービス管理責任者
専門の人材紹介エージェントです。
経験・人柄・専門性を備えた優秀な人材にアプローチし、採用の負担軽減と
サービス品質の向上を支援します。
- 登録料・掲載料が無料
- 採用実績豊富
- 全国対応
浜松市 障害福祉施設サービスの最新動向を把握しよう
浜松市では障害福祉サービスの需要が年々変化しており、施設運営者にとっては地域の実情を把握することが不可欠です。
ここでは、障害者手帳の所持者数や施設数の推移、サービス利用実績と見込みに注目し、浜松市の障害福祉の現状をデータから読み解きます。
浜松市における障害者手帳保持者数とその推移状況
浜松市における障害者手帳保持者数は、令和元年(2019年)から令和5年(2023年)までの5年間でわずかに増加傾向にあります。
身体障害者手帳は減少している一方で、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳の所持者が増加しており、知的・精神障害への理解の広がりや、診断機会の増加が背景にあると考えられます。
浜松市 障害者人口の推移 (手帳保持者数)
表が画面からはみ出す場合、左右にスクロールしてご覧いただけます。↔
| 障害者手帳の種類 | 令和元年 (2019年) |
令和2年 (2020年) |
令和3年 (2021年) |
令和4年 (2022年) |
令和5年 (2023年) |
過去5年間 増減率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 25,709人 | 25,565人 | 25,246人 | 24,927人 | 24,436人 | -5.0% |
| 療育手帳 | 7,248人 | 7,540人 | 7,775人 | 8,020人 | 8,289人 | +14.4% |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 6,181人 | 6,567人 | 6,765人 | 7,241人 | 7,615人 | +23.2% |
| 合計 | 39,138人 | 39,672人 | 39,786人 | 40,188人 | 40,340人 | +3.1% |
出典:浜松市 資料編1 障がいのある人の状況
データは延べ人数であり、複数の手帳を所持しているケースも含まれるため、単純合算ではありません。
浜松市内の障害福祉施設数と種類別分布
浜松市ではすべての障害福祉施設種別で事業所数が増加しており、とくにグループホーム(共同生活援助)の伸びが顕著です。
地域での生活を希望する障害者の増加や、グループホームのニーズの高まりが背景にあると考えられます。
浜松市 障害福祉施設数
表が画面からはみ出す場合、左右にスクロールしてご覧いただけます。↔
| 施設の種類 | 令和3年 (2021年) |
令和4年 (2022年) |
令和5年 (2023年) |
令和6年 (2024年) |
令和7年 (2025年) |
|---|---|---|---|---|---|
| グループホーム | 35事業所 | 40事業所 | 51事業所 | 58事業所 | 59事業所 |
| 就労継続支援A型 | 26事業所 | 27事業所 | 31事業所 | 31事業所 | 30事業所 |
| 就労継続支援B型 | 56事業所 | 59事業所 | 65事業所 | 69事業所 | 73事業所 |
| 就労移行支援 | 24事業所 | 24事業所 | 26事業所 | 26事業所 | 26事業所 |
| 生活介護 | 61事業所 | 67事業所 | 71事業所 | 73事業所 | 72事業所 |
出典:障害福祉サービス等情報公表システムデータのオープンデータ(2024年9月時点)
本データはWAMネット掲載のオープンデータを基に作成しています。自治体公表の数値とは異なる場合があります。
浜松市の障害福祉サービス利用実態
浜松市における障害福祉サービスの利用者は年々増加しており、令和8年(2026年)には5,400人を超える見込みです。
なかでも生活介護と就労継続支援B型の利用が多く、日常生活や軽作業による支援ニーズの高さがうかがえます。
一方、グループホームや就労移行支援も着実に増加しており、地域生活や一般就労を見据えた支援体制の強化が求められています。
浜松市 障害福祉サービス利用状況 (実績と見込み)
表が画面からはみ出す場合、左右にスクロールしてご覧いただけます。↔
| 施設の種類 | 令和4年 (2022年) |
令和5年 (2023年) |
令和6年 (2024年) (見込み) |
令和7年 (2025年) (見込み) |
令和8年 (2026年) (見込み) |
|---|---|---|---|---|---|
| グループホーム | 706人 | 750人 | 796人 | 848人 | 903人 |
| 就労継続支援A型 | 687人 | 709人 | 731人 | 754人 | 778人 |
| 就労継続支援B型 | 1,401人 | 1,441人 | 1,483人 | 1,525人 | 1,569人 |
| 就労移行支援 | 327人 | 349人 | 372人 | 396人 | 423人 |
| 生活介護 | 1,648人 | 1,683人 | 1,719人 | 1,756人 | 1,794人 |
出典:浜松市 第3章 福祉サービスの見込量《第7期障がい福祉実施計画》1
※令和6年度以降の実績は記事投稿時(2025年5月時点)でまだ公開されてないため見込みとなります。
浜松市の障害者施設 市場動向とニーズ分析
浜松市における障害者施設運営を検討する際には、地域ごとの需給バランスや将来の利用見込みを把握することが不可欠です。
この章では、施設種別ごとの充足率や将来的なニーズの変化に着目し、どの施設に開設の可能性があるのかを客観的データをもとに分析していきます。
障害者施設の種類別に見る将来の充足・不足状況(グループホーム・就A・就B・就労移行・生活介護)
浜松市では障害福祉サービスの利用者増加に伴い、施設の供給と需要のバランスに変化が生じています。
令和8年(2026年)時点の見込みデータによると、就労系支援を中心に不足傾向が見られ、今後の施設整備に向けた重要な判断材料となります。
このあと、各施設種別ごとの将来的な充足・不足状況を詳しく見ていきます。
浜松市 障害福祉サービスの充足率と需給状況
表が画面からはみ出す場合、左右にスクロールしてご覧いただけます。↔
| 障害者施設の種類 | 定員 令和7年 (2025年3月時点) |
令和8年 (2026年) |
||
|---|---|---|---|---|
| 利用者数 (見込み) |
充足率 | 供給状況 | ||
| グループホーム | 1,079人 | 903人 | 84% | 充足 |
| 就労継続支援A型 | 604人 | 778人 | 129% | 不足 |
| 就労継続支援B型 | 1,567人 | 1,569人 | 100% | やや不足 |
| 就労移行支援 | 383人 | 423人 | 110% | 不足 |
| 生活介護 | 1,965人 | 1,794人 | 91% | やや充足 |
出典:障害福祉サービス等情報公表システムデータのオープンデータ(2025年3月時点)
出典:浜松市 オープンデータカタログ グループホーム(2025年5月2日更新)
<供給状況について>
充足率は定員に対する利用者の割合です。110%以上は「不足」、100%~109%は「やや不足」、90%~99%は「やや充足」、89%以下は「充足」と評価しています。
この充足率は、浜松市における施設整備やサービス提供計画を検討する上での参考指標としてご活用ください。
充足率から開設すべきかを見極める障害者施設を種類別に解説
グループホーム(共同生活援助)の需要動向
令和8年の見込みでは充足率は84%であり、現時点では供給が足りていると判断されています。
ただし、利用者数は着実に増加しており、将来的な拡充の余地を見据えた検討が求められる分野です。
就労継続支援A型の需要動向
充足率は129%と高く、供給が明らかに追いついていません。
障害者の雇用機会の拡大に伴い、A型事業所へのニーズは今後も続くと考えられ、事業者にとって開設メリットは大きいでしょう。
就労継続支援B型の需要動向
充足率は100%と一見適正に見えますが、わずかな利用者増でもすぐに供給不足に転じる可能性があり、早期に対応を検討すべき段階に差しかかっているといえます。
就労移行支援の需要動向
就労移行支援は現在、不足傾向にあり、充足率は110%と供給が需要を下回っています。
特に若年層や発達障害のある利用者が増加する見込みであり、多様なニーズに対応できる柔軟な支援プログラムや、就労先との連携体制を備えた事業所の開設が求められています。
生活介護の需要動向
生活介護は充足率91%で「やや充足」と評価されています。
ただし、高齢化の進行や重度障害者の支援ニーズの拡大を踏まえると、今後の需要増も想定され、慎重な判断が求められます。
浜松市で障害者施設を開設するメリットとは?
障害者施設の開設は、地域のニーズと支援体制を見極めることが重要です。
浜松市には他地域にはない魅力的な支援制度や環境が整っており、施設運営者にとって有利な点が多くあります。
ここでは、補助金制度・人材確保・多文化対応という3つの観点から、その具体的なメリットを解説します。
浜松市の障害者施設向け補助金を紹介
浜松市では障害者施設の整備や運営に対して、市独自の補助金制度を複数展開しています。
ここでは、施設運営者が活用できる代表的な2つの補助金についてご紹介します。
-
浜松市の主な障害者施設関連補助金
- 障害者施設整備費助成事業:
- 浜松市障害福祉サービス等事業所物価高騰対策助成事業費:
社会福祉法人などが行う障害者福祉施設の新設・増築・改修などに対して、市が整備費用の一部を補助する制度です。
バリアフリー化や設備の老朽化対応など、地域のニーズに即した整備が補助対象となります。
補助率・上限:年度により異なるため、市の公募要領を確認してください。
申請期間:例年4月〜6月頃に募集(年度により変動)
物価上昇による光熱費等の負担を軽減するため、市内の障害福祉サービス事業所に対して交付される補助金です。
生活介護や居宅介護、相談支援など複数のサービス区分が対象となり、定員に応じて補助額が設定されています。
補助率・上限:補助率10割(全額補助)、補助額は定員等により変動
申請期間:令和7年3月頃より順次支給予定(詳細は市の通知にて案内)
各補助金制度は年度によって内容や条件が変更される場合があるため、申請前には浜松市の公式サイトまたは担当課にて最新情報をご確認ください。
福祉人材確保のしやすさ:浜松市内の採用環境
浜松市は静岡県西部の中核都市として、福祉分野における人材供給力も高い地域です。
地域内には福祉系の専門学校や医療・看護系の教育機関が複数あり、新卒採用をはじめとした地元人材の確保がしやすい環境が整っています。
また、浜松市では福祉人材バンクや合同就職面接会といった採用支援イベントも実施されており、民間事業所も積極的に活用しています。
全国的に人材難が課題とされる中、浜松市は比較的採用活動の選択肢が多い地域といえるでしょう。
多文化共生の進展により外国人スタッフ・利用者支援がしやすい
浜松市は全国でも有数の外国人住民数を誇る自治体であり、市として多文化共生政策を積極的に進めています。
この背景から、障害者福祉の現場においても外国人スタッフの雇用や、外国籍の利用者に対応した体制づくりがしやすい環境にあります。
実際に、市内の福祉施設ではポルトガル語やスペイン語、英語対応ができるスタッフが活躍しており、言語や文化の壁を乗り越えた支援体制が進行中です。
こうした多文化対応力は、浜松市ならではの強みであり、外国人を対象とした支援ニーズにも柔軟に対応できる施設運営が可能となります。
浜松市の主要連携機関一覧|開設・運営時に活用したいネットワーク
障害者施設の円滑な開設と質の高い運営を実現するためには、地域社会に根差した多様な機関との連携が不可欠です。
静岡県浜松市には、行政から医療、教育、地域団体まで、施設運営を力強く支援するネットワークが存在します。
この章では、特に重要となる連携先を具体的に紹介し、それぞれの機関とどのように協力関係を築いていくべきか解説します。
行政機関(市役所・関連部署)
施設開設の指定申請、補助金の相談、運営基準の確認など、事業の根幹に関わる手続きや相談に対応するのが行政機関です。
浜松市においては、以下の部署が主要な窓口となります。
-
浜松市役所の主な担当部署(例)
- 浜松市 健康福祉部 障害保健福祉課:
- 浜松市 保健所:
- 浜松市 市民部 UD・男女共同参画課:
障害福祉サービス事業所の指定申請・変更届、補助金に関する手続き、運営指導などを所管する中心的な部署です。
開設準備段階から運営に関する専門的な相談まで、幅広く対応しています。
感染症対策、衛生管理指導、精神保健福祉に関する相談(例:こころの健康相談)などで連携します。
特に精神障害のある利用者の支援において重要な役割を担います。
地域づくりや市民活動の推進、共生社会の実現などを所管し、地域包括ケアシステムの構築や福祉計画策定の側面での連携も視野に入ります。(※部署名は年度により変更される可能性があるため、最新の市組織図をご確認ください)
これらの行政機関とは、法令遵守はもちろん、地域の障害福祉施策の動向を把握するためにも、密接な連携を保つことが重要です。
地域の相談支援事業所との協力
相談支援事業所は、障害のある方々が適切なサービスを利用できるよう、サービス等利用計画の作成や関係機関との連絡調整を行う専門機関です。
施設運営者にとっては、利用者の紹介や受け入れ調整、個別支援計画作成における情報共有など、日常的な連携が欠かせないパートナーとなります。
-
浜松市における相談支援体制
- 浜松市障がい者基幹相談支援センター(浜松市基幹相談支援センター):
- 指定特定相談支援事業所:
地域の相談支援体制の中核として、市内の相談支援事業者への専門的な助言や後方支援、困難事例への対応、権利擁護の推進、関係機関との連携調整などを担っています。
事業者向けの研修会なども開催されることがあります。
浜松市内には、サービス等利用計画の作成やモニタリングを担う指定特定相談支援事業所が約 30 ヶ所(2025 年 5 月時点)存在します。
これらの事業所は、施設運営者にとって利用者紹介や支援調整を行う重要な連携先です。
最新の事業所一覧と連絡先は、
浜松市公式サイト 障害福祉サービス事業者一覧 で確認できます。
市内医療機関との連携体制構築
利用者の健康管理、急病や事故発生時の緊急対応、医療的ケアが必要な方への対応など、医療機関との連携は施設運営の生命線とも言えます。
浜松市内および近隣には、中核病院から地域のクリニックまで多様な医療機関が存在します。
-
浜松市内の主要な連携先候補(例)
- 浜松医科大学医学部附属病院:
- 聖隷三方原病院:
- 浜松市精神保健福祉センター:
- 地域のクリニック・歯科診療所:
高度・専門的な医療や救急医療を提供。
合併症を持つ利用者や重篤な状態になった場合の連携先として重要です。
地域の中核病院として、幅広い診療科を有し、入院や専門外来での連携が考えられます。
精神障害のある利用者への相談、診断、入退院支援などを担当。
専門医療機関との橋渡し的役割を果たします。
日常的な健康相談、予防接種、訪問診療などで連携する「かかりつけ医」「かかりつけ歯科医」の確保が望ましいです。
利用者の状態やニーズに合わせて、平時からの情報共有(診療情報提供書など)や緊急時の受け入れ体制について、具体的な連携方法を協議しておくことが重要です。
特別支援学校等、教育機関との連携
地域の教育機関との連携は、特に学齢期・青年期の利用者を支援する場合や、将来の福祉人材育成の観点からも重要です。
浜松市内および近隣には、特別支援学校や福祉系学科を持つ大学等があります。
-
浜松市内の連携候補となる教育機関(例)
- 静岡県立浜松特別支援学校:
- 静岡県立浜松視覚特別支援学校・静岡県立浜松聴覚特別支援学校:
- 静岡大学(教育学部など)、静岡県立大学短期大学部(看護学科など):
知的障害や肢体不自由のある生徒が対象。
職場体験実習の受け入れや、卒業後の進路に関する情報共有、移行支援で連携します。
視覚障害・聴覚障害のある児童生徒が対象。
それぞれの障害特性に応じた支援と施設との連携が求められます。
静岡大学では教育学部等で特別支援教育教員などの養成課程があり、静岡県立大学短期大学部では看護学科で看護師を養成しています。人材育成や研修・実習の場として連携可能です。最新の情報は各大学にご確認ください。
これらの教育機関と連携することで、利用者のスムーズな移行支援や、地域における人材育成に貢献できます。
ハローワーク・NPO法人等、その他の支援機関・団体との連携
行政、医療、教育以外にも、地域には施設運営を支える様々な団体が存在します。
これらの機関との連携により、地域資源の活用やネットワークの拡大が期待できます。
-
浜松市内の主要な関連機関・団体(例)
- ハローワーク浜松(浜松公共職業安定所):
- 浜松市社会福祉協議会(市社協):
- NPO法人 N-Pocket(浜松NPOネットワークセンター):
- 地域活動支援センター(市内複数):
就労系サービスにおいて、職業相談・紹介、職場開拓、各種助成金の活用などで密接に連携します。
地域福祉の中核組織。
ボランティアの紹介・調整、権利擁護事業など多角的な連携が可能です。
障害者・外国人・高齢者など多様な支援を行う地域密着型のNPO。
施設運営においても人的資源や地域連携の面で協力が期待されます。
日中活動の場の提供、地域住民との交流支援、生活支援等に関して連携可能です。
これらの多様な機関・団体と積極的に関わり、情報交換や協力体制を構築していくことが、地域に開かれ、信頼される施設運営の鍵となります。
【掲載無料】「貴施設の魅力を、浜松市の利用者様へ届けませんか?」
概要
日々の施設運営、誠にお疲れ様です。
当サイトでは、当記事とは別に、浜松市の障害者の利用者様やそのご家族に向けたお役立ち記事を運営しております。
つきましては、その記事内で「浜松市のおすすめ施設」として、貴施設の活動を完全無料でご紹介したく、ご協力くださる事業所様を募集しております。
未来の利用者様へ貴施設の魅力を直接アピールできる絶好の機会です。
なお、記事の品質と情報量を適切に保つため、ご紹介できる施設様の数には限りがございます。
続きを読む
費用
費用は一切かかりません。
掲載
ページ
掲載場所につきましては、記事内の下部、まとめ見出しの直上の位置を予定しております。
お願い
当サイトでは、読者の皆様に信頼性の高い情報をお届けすることを何よりも大切にしております。
そのため、掲載させていただくにあたり、施設の公式サイトを運営されていることや、情報が確認できることなど、
いくつか簡単なお願いをさせていただく場合がございます。
ご応募
ご興味のある施設様は、お手数ですが、下記の情報をご記入の上、専用のお問い合わせページよりご連絡ください。
担当者より、折り返し詳細をご案内させていただきます。
まとめ
浜松市で障害者施設を開くときは、「どんなサービスが足りていないか」を数字で確かめることが出発点です。
この記事では、定員と利用見込みから不足している分野を示し、あわせて市の支援策や連携先を紹介しました。
最後に、これらの情報をどう活かせば良いかを3つの手順で整理します。
-
開設を成功に近づける3ステップ
- 1. データでニーズを確認
- 2. 補助金と人材で計画を後押し
- 3. 連携先と早めに顔合わせ
市の整備費助成や光熱費補助を活用し、地元の福祉系学校から人材確保のめどを立てましょう。
障害保健福祉課、医療機関、相談支援センターなどに事前相談し、協力体制を整えると開設後も安心です。
3ステップを活用すれば、データで裏づけた計画と地域に根差す運営の両立がぐっと近づきます。
最新データを定期チェックしつつ、障害保健福祉課や基幹相談支援センターを頼りに、一歩ずつ形にしていけることを願っています。
新しい施設が地域の選択肢を広げ、利用者の未来を照らすことを願っています。